更新日:2025年9月2日
16分で読めます
APIとは?意味や利用のメリット、注意点、活用事例を徹底解説
API連携の仕組みやメリット、注意点を解説します。APIの種類や具体的な活用例も解説します。

ソフトウェア開発の領域においては「API」の活用が注目されています。APIを導入することで開発コストの削減や効率化、高度な機能実装などを実現できます。
しかし、APIといってもさまざまな種類があり、意味や仕組みについて詳しく理解していない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、API連携の仕組みやメリット、注意点を解説します。APIの種類や具体的な活用例も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
1. APIとは?

API連携は、その名の通り、APIを利用してアプリケーションの機能やデータを他のアプリケーションやシステムと連携させ、利用できる機能を拡張することです。事前登録したクレジットカードから自動決済されるシステムやカレンダー機能を使った自動予約システムなどにもAPIが使われています。
API連携によって、プログラムをゼロから開発しなくても既存のソフトウェアやWebサービスが提供している機能を活用できるため、効率よく顧客体験を向上させることができるため、幅広い業界で活用が広がっています。
2. API連携のしくみ
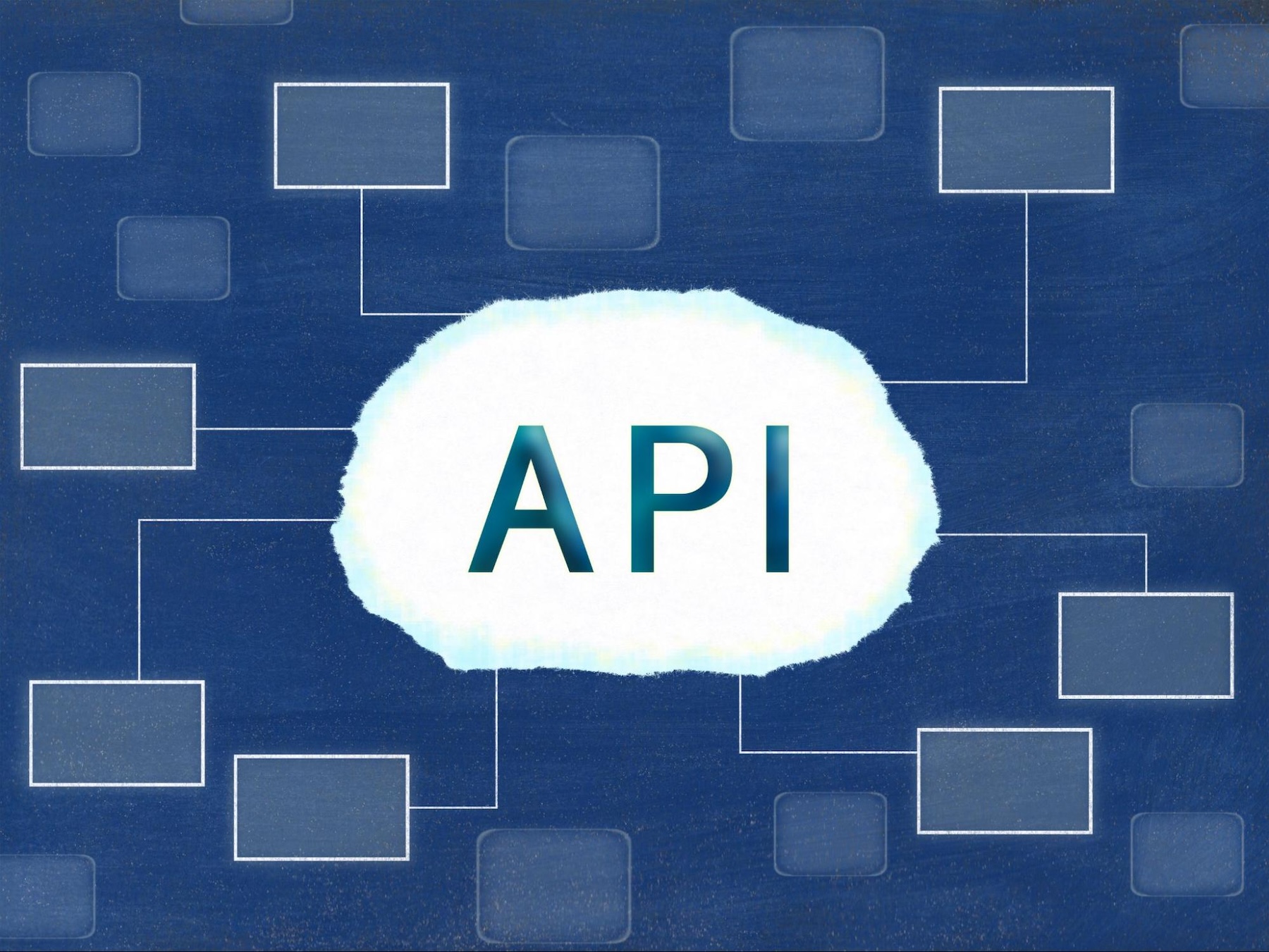
API連携はリクエスト(要求)とレスポンス(応答)で成り立っています。利用者側がリクエストし、提供元がレスポンスするという構図です。API連携のためには、APIの提供元は事前にどのようなリクエストに対してどのようなレスポンスを返すのかルールを設定しなければなりません。
利用者はそのルールに則ったコードを書くことでAPIを連携させることができます。
3. API利用のメリット

APIを自社のソフトウェア開発に導入することで以下のようなメリットを享受できます。
- 開発の効率化とコスト削減
- データの2次利用
- セキュリティの向上
- ユーザーの利便性の向上
3-1 開発の効率化とコスト削減
APIを活用することで開発の効率化とコスト削減を実現できます。通常新しい機能を開発する場合、要件定義から設計、開発、テスト、リリースまでを自社で実施する必要があります。そのプロセスにおいて自社が求める機能を提供しているAPIと連携すれば、複雑なプログラミングを要してゼロから開発する必要がなくなるため、スピーディーに高度な機能を実装することが可能です。
なお、多くのAPIは無料で提供されていますが、有料のAPIであっても自社でゼロから開発した場合に発生するコストと比べれば、低コストで開発を進められるでしょう。
3-2 データの2次利用
無料で提供されているAPIも多くありますし、有償APIも自社で開発から構築まで取り組んだ場合にかかる費用と比べれば、低コストに抑えられることがほとんどです。
API連携によって他社サービスのデータを利用できます。例えば、ECサイトで提供されているAPIなら、ECサイトが保有している商品情報や在庫状況、顧客情報などを取得して自社のマーケティング戦略に活かせるでしょう。また、SNS業界でもAPIの公開が進んでいます。ユーザーの投稿やトレンドを分析すれば、新しい機能開発にもつなげられます。
APIの活用により膨大なデータの収集から登録、更新まで行う必要がないため、業務効率化や情報の信頼性向上が期待できます。
3-3 セキュリティの向上
近年セキュリティインシデントが多く発生しているため、自社でシステムを構築する際にもセキュリティ強化を徹底しなければなりません。API連携を行えば、開発におけるセキュリティ強化にもつなげられます。
例えば、モバイルデバイスを利用した二段階認証をシステムに構築する場合、自社で構築・運用するよりもAPI連携で実績のある認証サービスを利用すれば、セキュリティレベルの高い二段階認証を導入できます。これによりユーザーも安心してシステムに登録できるため、登録ユーザー数の向上も期待できるでしょう。
3-4 ユーザーの利便性の向上
API連携を行えば、ユーザーの利便性向上も見込めます。例えば、自社のWebサービスをユーザーが初めて利用する際に登録情報の入力が面倒だと感じることも多いでしょう。
そこでAPI連携によって他社サービスの登録情報を活用して登録・ログインできる仕組みを構築しておけば、ユーザーはスムーズにサービスを利用することができ、「登録・ログインの手間」による離脱防止につなげられます。
4. APIを利用する際の注意点

APIにはさまざまなメリットがありますが、以下のような注意点もあるため利用前に把握しておくことが大切です。
- サービスの不具合の可能性
- 突然のサービス停止のリスク
4-1 サービスの不具合の可能性
API提供元でシステムの不具合が発生した場合、自社で連携しているAPIの機能が使えなくなる可能性があります。つまり、APIを安定的に継続して活用できるかどうかはAPI提供元に大きく依存するということです。
万が一、トラブルが発生し機能が使えなくなった場合は自社での対応はできないため、解消されるまで待たなければなりません。システムの利用ユーザーに不安や不満を感じさせてしまう原因にもなるため、事前にリスク対策を検討しておくことが大切です。
4-2 突然のサービス停止のリスク
API提供元のシステムの不具合だけでなく、サービスそのものが停止される可能性も考慮しておく必要があります。
機能そのものが停止してしまうと、自社のサービスでも利用できなくなるため、代替となるサービスを活用する必要があります。
突然サービスが停止されてから新しいAPIを探して実装するとなると時間と手間がかかるため、あらかじめ調査しておくことをおすすめします。
5. APIの種類

APIには提供される目的や用途に応じていくつかの種類があり、いずれも提供元や活用方法が異なります。どのAPIを使うのが最適か判断するためにも、APIの種類について理解しておきましょう。
5-1 Web API
Webを介して機能の一部が提供されるAPIです。「HTTP/HTTPS」の通信方式を使ってインターネット経由でリクエスト/レスポンスのやり取りが行われます。プログラミング言語や使用するパソコンのOSに関係なく、あらゆる環境からアクセスが可能な点が大きな強みであり、多くの企業からさまざまなAPIが提供されています。
5-2 OS API
WindowsやAndroidのようなOSが提供する「OS API(ネイティブAPI)」。OSが持っている機能を、他のアプリケーションでも呼び出すことができるAPIです。WindowsがOSとして持っている機能をサードパーティ製のアプリでも使えるようにしています。OSが進化するとともに、OSが提供する機能は多岐にわたり、手軽にAPIを使えるようなツール(フレームワーク)が提供されることも増えています。
5-3 ライブラリAPI
ライブラリAPIとは、プログラミング言語のライブラリが提供するAPIのことで、クラスライブラリやコアAPI、標準APIとも呼ばれる場合もあります。ライブラリには、外部から利用できる特定の機能を実装するためのプログラム部品が格納されており、APIとして利用すれば一からコードを記述する必要がなくなるため、開発効率を大幅に向上させることが可能です。
つまり、ライブラリAPI を活用すれば複雑なプログラミングを短時間で実行できるようになります。
5-4 ランタイムAPI
ランタイムAPIとは、プログラムが実行されている時に使用されるAPIで、プログラム実行中の情報を取得できます。例えば、アプリケーションの動作状況をリアルタイムで把握し、メモリの使用量や実行時間などを把握することが可能です。
ランタイムAPIを活用すれば早期にアプリケーションの状態を把握できるため、問題の早期発見・改善につながりパフォーマンスを最適化できます。
6. APIの提供方式

APIにはさまざまな提供方式があり、活用の目的によって使い分ける必要があります。
- オープン(パブリック)API
- パートナーAPI
- 内部API
- コンポジットAPI
6-1 オープン(パブリック)API
オープンAPIは、企業が運用しているシステムのAPIを外部に公開しているAPIを指します。API提供元の企業はAPIを外部公開することで自社サービスの認知拡大を図れ、さらにAPIの提供を有料コンテンツとすれば利益の確保にもつながります。
API利用者側は利用規約に同意すれば誰でも利用できるため、システム開発の際に自由に連携することが可能です。これにより高度な機能実装やセキュリティ向上を実現できます。
6-2 パートナーAPI
パートナーAPIは、企業間で利用されるAPIを指し、オープンAPIとは異なり外部での利用が限定されるのが特徴です。
パートナーAPIを利用すれば、パートナー企業が保有しているデータや機能といったリソースを最大限に活用できるため、自社システムのパフォーマンス向上や顧客体験の強化につなげられます。
6-3 内部API
内部APIは、企業内のシステム間でデータのやり取りをするために活用されるAPIを指します。社内向けのAPIであるため、外部に公開されることはありません。
多数のシステムを保有している企業なら内部APIを整備することで、社内でのデータ連携が容易になるため業務スピードの向上を実現できます。
6-4 コンポジットAPI
コンポジットAPIとは、一つのAPIで複数のAPIをまとめて利用できる形式のことです。コンポジットAPIを活用すれば、複数のアプリケーションとデータ連携する際の負担が軽減されるため開発効率の向上が期待できます。
クラウドサービス間のデータ連携においてコンポジットAPIが利用されることが多いです。
7. 代表的な4つのAPIプロトコル

APIプロトコルとは、システム間でデータの送受信を行うための通信の仕組みを指します。代表的なプロトコルは以下が挙げられます。
- HTTP / HTTPS
- XML-RPC
- JSON-RPC
- SOAP
7-1 HTTP / HTTPS
HTTP / HTTPSは、WebサーバーとWebブラウザとの間でデータのやり取りをするために用いられるプロトコルを指し、多くのWeb APIで利用されています。
HTTPSは、通信内容が暗号化されるためHTTPよりも高いセキュリティでより安全な通信を実現できます。
7-2 XML-RPC
XML-RPCは、XML形式を利用してクライアントとサーバー間でデータのやり取りをするプロトコルです。RPC(Remote Procedure Call:リモートプロシージャコール)とは、ネットワーク上にある他のコンピューターに対して処理をリクエストして実行するための手法を指します。
XML-RPCは、1998年にユーザーランド・ソフトウェア社とマイクロソフトが共同開発したもので後に紹介するSOAPへと発展しています。
7-3 JSON-RPC
JSON-RPCとは、JSONを利用してクライアントとサーバー間でデータのやり取りをするプロトコルを指します。
JSONは可読性が高く、コンピューターにとっても扱いやすい軽量のデータフォーマットであるため幅広く利用されています。
7-4 SOAP
SOAPとは、「Simple Object Access Protocol」の略語のことでXML-RPCを拡張したプロトコルです。SOAPはデータをやり取りするためのルールが厳格に定められているため、XML-RPCと比べて複雑なデータの通信に使われます。例えば、決済や認証など高いセキュリティが求められるシーンで活用できます。
8. API連携の具体例

具体的にどのような場面でAPI連携が使われているのでしょうか。
- SNS
- ECサイト
- POSレジ
- 地図・天気情報
以上4つの例を具体的に説明します。
8-1 SNS
近年、SNSは企業と個人をつなぐツールとして不可欠な存在となりつつあります。世界中に顧客を持つ企業では、よりきめ細かなカスタマーケアを提供する方法としてX(旧Twitter)で公開されているAPI「Sprout Social」はDM(ダイレクトメール)やメンション、リプライなどで言及されたユーザーからの要望や質問を、企業内の担当者に直接転送してくれます。
また、カスタマーフィードバック機能では、XのDMで製品やサービスの満足度に関するアンケート調査を行えます。質問への回答率の向上や解答までの時間短縮が顧客体験の向上を実現します。他にもLINEを使った荷物の再配達設定など、SNSを使った顧客体験の向上は広い業界に広がっています。
8-2 ECサイト
決済サービスの運営事業者はECサイト向けのAPIやサードパーティアプリを提供しています。例えば、楽天ペイでは決済処理APIを提供しており、API連携をしたECサイトで楽天会員が決済する場合、楽天ペイに登録済みの情報を呼び出して決済できます。個人情報を入力して会員登録をする手間を省けるため、顧客体験やコンバージョン率の向上が見込めます。
8-3 POSレジ
販売情報を集計・記録するPOSレジでもAPI連携が広がっています。顧客管理システムとの連携で会員情報の共有や購買履歴にあわせた商品レコメンドが可能になります。また、在庫管理システムとの連携で仕入れ効率を向上するなどデータ管理の効率化でも使われています。業種や店舗形態によってさまざまな活用が広がっています。
8-4 地図・天気情報
自社のWebサイトやアプリに対して、地図や天気情報をAPI連携を通して反映させることができます。
例えば、商品の認知拡大や購買意欲の向上を目的として屋外イベントを開催する際には、API連携してWebサイトに地図や天気情報を掲載して告知すればユーザーに有益な情報を提供できます。これによりユーザーの情報収集の手間が省けるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
9. 注目のAPI提供元とそのサービス

ここからは、注目のAPI提供元をご紹介します。
9-1 Google
Googleでは、クラウド基盤である「Google Cloud Platform」上で、利用できるAPIをライブラリにまとめており、GmailやMap、YouTube、Calendar、Driveの他、300種類のAPIが公開されています。
こうしたAPIを使って、メールを簡単に取得するツールやカレンダーアプリを作ったり、ブラウザの拡張機能や画像認識を使ったスマホアプリ、ソフトウェア、Webサービスを構築できます。
9-2 X(旧Twitter)
大手SNSであるXもAPIを提供しています。Webサイトに表示される投稿内容や投稿をまとめたり、自動で投稿してくれるツールなど、全てAPIをベースに作られています。
SNSを使った情報発信や、情報収集を効率化したい場合には、真っ先にチェックすべきAPIと言えるでしょう。
9-3 OpenAI
話題のChatGPTを提供するOpenAIもAPIを提供しています。画像生成、機械文字起こし、自動分類、機械学習を実装するAPIに注目が集まっています。
9-4 ヤマト運輸
WebAPIにより、配送連携APIを提供しています。二次元コードをかざすだけでコンビニやオープン型宅配便ロッカーからの荷物を発送するため、匿名配送や発送時の支払い簡略化が可能になり、高い顧客満足を誇っています。
9-5 Slack
アメリカ発のビジネス向けコミュニケーションツールであるSlackも、「Slack API」という独自のAPIを提供しています。利用することで、リマインドやリアルタイムでのアラートなどの通知が行えます。Botを活用し、タスク自動化、メッセージの送受信や会話へのリアクションなども実装できます。
Slackへ外部サービスからのAPIも提供されており、例えばGitLabもSlack向けのAPIを提供しています。
10. APIの使い方・利用手順

- API提供元のWebサービスに登録する
- APIキーとAPIシークレットを取得し設定を行う
- 実装・テストを行う
多くの場合、まずAPIを提供しているWebサービスへの登録が必要になり、基本情報の入力を行います。登録が完了すればAPIキーとAPIシークレットを取得できます。これらはAPIを利用するためのコードであるため大切に保管しておいて下さい。
コードの取得まで終わり、準備が整えば実装の段階に移ります。APIの実装手順は提供事業者によって異なるため、ドキュメントなどを確認しながら行いましょう。実装が完了したら実際に操作してみて動作に問題がないか確認します。
11. API連携に関するよくある質問

最後にAPI連携に関するよくある質問とその回答を紹介します。
11-1 APIゲートウェイとは何ですか?
APIゲートウェイとは、APIの管理ツールです。複数のAPIと連携を行う場合、APIゲートウェイを使えば、APIゲートウェイがそれぞれのAPIへリクエストを振り分け、集約し適正なレスポンスを返却してくれます。
11-2 APIは誰でも利用できますか?
基本的には誰でも利用可能です。ただし、利用における必要な技術や、APIによっては有償化されているものもあるので、利用する際には、きちんとした理解と検討が必要です。
11-3 RESTとSOAPの違いは?
RESTは「Representational State Transfer」の略語であり、Webのアーキテクチャスタイルの一つです。HTTPプロトコルを使用しますが、REST自体はプロトコルではありません。
一方、SOAPはメッセージングプロトコルであるため、両者は根本的に異なるアプローチだといえます。
11-4 WebhookとAPIとの違いは?
WebhookとAPIにおいては、どちらもアプリケーション間でデータを連携するために活用されますが、両者は仕組みの観点から明確な違いがあります。
APIの場合は、必要に応じてデータをリクエストしてレスポンスを受け取る方式ですが、Webhookは事前に設定した条件を満たすことでこちら側からリクエストしなくてもレスポンスを受け取れます。
つまり、Webhookならリアルタイムで必要な情報を受け取ることができます。しかし、APIとは異なりユーザーを認証する機能がないため、悪意ある情報を受け取ったりなどセキュリティにおけるリスクがあります。
まとめ 自社のビジネスやサービス開発にAPI戦略を取り入れよう!
自社のソフトウェア開発やビジネスにおいてAPIを積極的に活用することで、開発効率の向上やコスト削減などを実現できます。
APIにはさまざまな種類がありますが、自社に必要な要件を満たしたAPIを探して積極的に開発に取り入れていくと良いでしょう。
GitLabでも開発者向けに包括的なAPIを提供しており、CI/CDパイプラインの自動化から課題管理まで、様々な機能をAPI経由で利用できます。GitLabの利便性の高いAPIを、ぜひこの機会に体験して下さい。
なお、GitLabでは世界39か国、5,000人を超えるDevSecOps専門家のインサイトが詰まった完全版レポートを無料で公開しているので、ぜひこちらもご覧ください。
